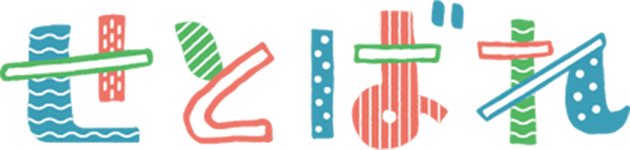これから
「おめでとうございます」
これほどまでに嬉しい電話の始まりがあるだろうか。
私の書いた小説が、新人賞をとったのだ。
数週間前に最終候補に残ったという知らせがあってから今日まで、毎日そわそわしていた。賞に入らなかった時は何の連絡もないと聞いていたので、今朝から5分に一度は時計の針を眺めていたと思う。
数年前にも、またちがう新人賞一歩手前まで来たことがあって、その時は母もいっしょに電話を待ってくれた。いつまで経っても鳴らないスマホをじとっとした目で二人で見つめていたのも、今となってはいい思い出だ。
「お母さん、やったよ」
今日、受賞の電話を切って思わず高い声を出してしまったけれど、母は隣にもこの世にももういない。
子どもの頃から本が好きで、小説家を目指してきた。結婚して家庭をもったり、大きな仕事を任せられるようなキャリアを着実に積んでいく友人達の中には、話が合わなくなってしまった人もいる。でも、母はずっと応援してくれていた。
「受賞するの、遅くなっちゃったね」
スマホの中の母の写真に向かってつぶやく。
「ううん。お母さんが早かったんだよ」
とか文句も言ってみる。写真の母は、いつもより美しく笑っているように見えた。
「緑さん、おめでとう」
数週間後、私が所属している作家志望が集まるサークルのみんなが、お祝い会を開いてくれた。講師のプロの先生が、まっさきにこう言ってくださって、ほんとに受賞したんだと実感した。
「ありがとうございます。つづけてきて、よかったです」
私の言葉に、先生も周りの仲間達も大きくうなずいてくれた。
「受賞したのって、この前の合評会に出していた東かがわ市のお話ですか?」
一番若い、まだ20代の仲間はそう言って、ワインをグラスになみなみと注いでくれた。
「そうなの。また今度あっちに行って、お世話になった方々にお礼を言わなくっちゃ」
「その時は、私も連れてってください」
「じゃ、誘うわね」
受賞のお祝い会は、これまで何回か参加したことがあったけれど、自分が主役になる日がくるなんてなぁ。
乾杯から始まり、大きな花束をもらい、ペンやかわいいメモ帳、付箋など、作家業に欠かせないようなプレゼントもたくさんいただいて、おまけにお酒もいつもより飲んだので、体も心も熱くなっていた。夜が更けて閉会してから会場を出ると、熱帯夜のはずなのに夜風が気持ちよく感じた。
「やっとここまで、来られたなあ」
なんて独り言を言いながら、夜道を歩く。手にはお花、腕にはプレゼントの入った紙袋がたくさんぶらさがっている。でも全然重く感じないのが不思議だ。
「いっしょにお祝いしてほしかったなぁ」
首には、生前母がくれたストール。私の名前にちなんで緑の……カーキ色のもの。
見上げると、満天の星……なんてのは見えなかったけれど、いくつかは輝いていた。
いいんだ。私はもう、見えないところにも星があるって知ってる。そう信じてきたからこれまで頑張ってこられたんだ。
「これからよ」
目をつぶると、母の声が聞こえた気がした。
そうだよね。小説家って、書き続けなきゃ小説家でいつづけられないんだ。
私はやっと、スタートラインに立ったってだけ。
ストールがなびくくらい速く……は走れなかったけれど、私は駆け出した。
荷物がガサゴソ音を立てて、花がワサワサ揺れて、心臓はこれまで生きてきて一番高鳴った。
見てて、お母さん。
これからも、ずっと。